小説「懺悔」 第一章・・・

『懺 悔』 紅殻格子
一.
日曜日の夜。
煌々とシャンデリアが燈るリビング・ダイニングで、一家団欒の夕食が始まりました。
今夜は私の得意なパスタ料理です。
特にホワイトソースとトマトソースを交互に重ねて焼くラザニアは、知り合いのイタリア人シェフに教えてもらった本格派です。
夫の貴彦がおどけたように言いました。
「美味い。ママが作るパスタは三ツ星レストランも顔負けだ。なあ、智彦」
「うん、いつ食べてもこのラザニアは最高だよ」
主人や子供に料理を褒められるのは、幾つになっても主婦として嬉しいものです。
「んもう、いくらお世辞を言ってもお小遣いは増えないわよ」
私が冗談めかして答えると、主人と息子はお腹を抱えて大笑いしました。
温かな笑い声が吹き抜けになった三十畳ほどのリビングに反響します。
五年前に新築したこの家は、ここ横浜の高級住宅街でも、一際目立つお洒落なデザイナーズハウスです。
土地も六十坪と広く、芝生を敷きつめた庭園の入り口には、つる薔薇を絡ませたアーチが立っています。
夫の貴彦は四十二歳、一流大学を卒業して都市銀行に勤務しています。
息子の智彦は高校一年生、進学校として県内でも有名な私立学校に通っています。
そして私は三十八歳、結婚して十七年になる主婦です。
明るい家族と経済的にも恵まれた生活――傍目にはこの上なく 幸せな家庭に見えるのでしょう。
友人や近所の奥さん達も、私を羨望の眼差しで見ているようです。
でもこの幸せは幻影なのです。
束の間の団欒は、貴彦、智彦、そして私が、それぞれ家族と言う仮面をつけて演じているお芝居なのです。
夕食が終わると、主人がスーツに着替え始めました。
「十一月になると仙台はもう真冬だよ。コートを送っておいてくれないか」
今年の四月、貴彦は仙台支店へ副支店長として異動しました。
智彦の学校があるので単身赴任です。
貴彦は金曜日の深夜に横浜へ帰宅し、日曜日の夜、最終の東北新幹線で仙台へ戻って行きます。
横浜・仙台の往復交通費は、月二回分だけ単身赴任手当てとして支給されます。
最初の頃はきちんと月二回家へ帰ってきた貴彦ですが、
今では仕事が忙しいと言って月一回しか戻って来ません。
でも仕事が忙しいのは嘘です。
仙台に女がいるのです。
転勤した三ヶ月後、私は主人を訪ねて仙台へ行きました。
男の一人暮らしでは、食生活が心配ですし、掃除も行き届かないと思ったからです。
ところが借りているワンルームは、意外なほど綺麗に片付いていました。
不思議に思った私は、貴彦が銀行へ出社している間に部屋を家捜ししました。
そして生ゴミの中からルージュがついたタバコを見つけた時、私は全てを悟ったのです。
気が動転しました。
でも私は貴彦を責めませんでした。
何故なら、私自身も密かに主人以外の男性に想いを寄せていたからです。
実は貴彦が勤めているのは、経営破綻して公的資金を注入したX銀行なのです。
ご存知の通り、国民の税金を穴埋めして倒産を免れた代償は、行員の給料三割カット、賞与ゼロと言う厳しい処遇でした。
エリート銀行員だった主人の精神的ダメージは元より、家計も大きな打撃を受けざるを得ませんでした。
一番の足枷はこの家の住宅ローンです。
銀行破綻前に建てた家は、土地の価格も含めて約七千万円、 その大半をローンで賄っていました。
それに加えて智彦が有名私立高校に進学できたことで、入学金や寄付金、そして高い授業料と、家計は文字通り火の車となっていきました。
年収七百万円に対してローンの年返済額が三百万。
とても生活が維持できる状況ではありません。
しかし一度建てた家を売ることもできず、有名私立に受かった智彦を公立高校へ通わせるのも忍び難く、悩み抜いた挙句は専業主婦の私が働くこととなったのです。
つづく・・・










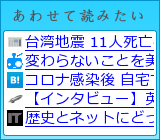


 を目指して…
を目指して…
 応援よろしくお願いします
応援よろしくお願いします



