小説「懺悔」 第二章・・・
『懺 悔』 紅殻格子
二・
でもそれが躓きの第一歩でした。
私がアルバイト先に選んだのは、隣駅にある小さな土建会社でした。
簿記一級の資格を持っていた私は、経理アルバイトを募集していた川和建設で働き始めました。
就職すると、鏡に向かって念入りにお化粧をするようになりました。
二十歳の頃は嫌いだった童顔も、三十路を過ぎると若々しい
愛らしさに変わって満更でもありません。
ウエーブのかかった肩まで伸びる髪、くりっとした円らな瞳、ちょっと鼻梁は低めですが、
キュートに微笑む口許――生活苦のために働き始めた私ですが、
専業主婦になって忘れかけていた女であることを、
再び取り戻した歓びを感じるようになっていたのです。
でもアルバイトとは言え、結婚前一年間しかOLの経験がない私は、
なかなか会社に馴染むことができませんでした。
しかも社員二十名ほどの土建会社です。
半裸で汗臭い男達が、キャバレーのホステスを相手にするように卑猥な言葉をかけてきます。
「奥さん、ご主人単身赴任だって? 今夜寂しければ夜這してやろうか」
「おうよ、たまにはオマンコの煤払いをしないと、蜘蛛の巣が張っちまうぜ」
私が赤面して俯いてしまうと、決まって助けてくれるのは川和社長でした。
「馬鹿野郎! お前等のカカアと違ってこの人は上品な奥さんなんだよ。
言葉遣いに気をつけねえか!」
褐色に日焼けした厳つい体の川和社長は、まだ四十代半ばで、
パンチパーマにロレックスの腕時計を巻く典型的な土建屋の頭です。
インテリタイプの貴彦とはまったく違う強面な社長に、
最初のうちは私も生理的に抵抗がありました。
ところが外面とは違う社長の優しい気遣いに、
夫がいない寂しさもあったのでしょうか、私は徐々に惹かれて行ったのです。
ある夏の日、普段はほとんどないのですが、
月末の帳簿づけが滞って残業しなければならなくなりました。
やっと仕事が終えた時には九時を回っていました。
「夜遅いから家まで車で送ってやるよ」
たまたまその夜事務所にいた社長の親切に、私は何の警戒心も持たず甘えてしまったのです。
「ちょっとドライブして行こうか?」
ベンツの助手席でそう誘われた私は、家で待っている智彦が心配でしたが、
浮気している主人への当てつけもあってOKしてしまいした。
横浜でも郊外にはまだ雑木林が茂る丘陵が多く残っています。
社長はそんな人通りのない山道に車を停めました。
そして突然、社長が助手席の私に覆い被さってきたのです。
「い、いやっ!」
抗おうとしましたが、力の強い社長には敵いません。
いきなり私の顔を両手で押さえると、社長は強引に口唇を合わせてきました。
ぬるぬるした舌を絡められ、私は口を吸われました。
すると体がかっと熱くなって下腹部が疼き、主人のこと、智彦のこと、
全てのしがらみがふっと頭から消えてしまったのです。
妻であり母であることを捨て、一人の女に、いえ一匹の雌に戻った瞬間でした。
後は社長にされるがままでした。
ブラウスを剥がれて乳房を弄ばれ、スカートを捲られて陰部を嬲られました。
でも私はレイプされているのにはしたない喘ぎ声をあげていたのです。
「奥さん、よほど飢えていたんだな。もうぐっしょり濡れているぜ」
「あ、ああっ・・社長、だめ・・やめて・・」
確かに主人とはセックスレスの状態が十年近く続いていました。
でも私自身、男と女は年とともにそうなるものだと思っていました。
ところが社長の愛撫で、私の体は今までにないほど淫らに感じてしまったのです。
主人を裏切る背徳、熟れ盛りの体、
巧みな社長の愛撫――いろいろな刺激が一つの火の玉となって私を翻弄しました。
十年間の鬱憤を晴らすかのように、身も心も私は社長の愛撫を貪り求めていたのです。
社長はシートを倒して助手席に乗り移って来て、荒々しくショーツを剥ぎ取りました。
そしてズボンを下ろすと一気に男性を挿入してきたのです。
「あ、いやっ、許して・・うっ、うぐうぅぅ」
ヌルッとした感触とともに、膣いっぱいに社長の男性が入ってきました。
主人のものを受け入れた時より、遥かに膣が圧迫されているのがわかります。
「おう、凄えな。俺の自慢の一物をずっぽりと呑み込んじまった」
「い、言わないで・・」
「これでお前は俺の女だ」
社長はそう宣言すると、ゆっくりと腰を動かし始めました。
巨大な男性が出入りするたびに、陰部全体が押し込まれたり
捲り返ったりするような錯覚を覚えました。
「いいっ! き、気持ちいい!」
狂わんばかりの悦楽に、私は逞しい社長の体にしがみついていました。
ぎしぎしと車が揺れる中、時を忘れて社長に征服される歓びに身悶えたのです。
それ以来、私は社長の雌奴隷となりました。
社長は融資の交渉に銀行へ行くと嘘をつき、週に二三度、
仕事の途中に私を車に乗せて連れ出すようになりました。
そして会社から近いラブホテルで私の体を貪るのです。
私には主人がいますし、社長にも奥様がいらっしゃいます。
でも一度火がついてしまった肉体は、社長の逞しい男性でしか鎮めることができませんでした。
罪悪感を覚えながらも私は社長に溺れていきました。
社長の雌奴隷になる黒い愉悦から、麻薬のように体が離れられなくなってしまったのです。
つづく・・・










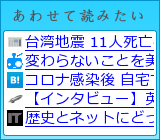


 を目指して…
を目指して…
 応援よろしくお願いします
応援よろしくお願いします



