小説 「妄想の仮面」 第六章・・・
※ 小説を読まれる方へ・・・
更新記事は新着順に表示されますので小説を最初から順追って
お読みになりたい方は、左のカテゴリーから各小説を選択していただければ
第一章からお読みいただけるようになっております ※
『妄想の仮面』 紅殻格子
六.妻の独白(三)
飲めないワインに、私はすっかり酔ってしまいました。
「お宅までお送りしますよ」
店を出ると、清川君はタクシーを止めて、抱きかかえるように私を乗せました。
「大丈夫ですか?」
「え、ええ・・ちょっと飲みすぎちゃったみたい・・」
私はタクシーの窓を開けて、涼しい初夏の風を入れました。
「もう十一時だわ・・あの人、もうお風呂に入ったかしら」
「おや、田口課長のことが心配ですか?」
「そ、そんなことないわ。私だってたまには夜のお酒ぐらい・・」
むっとむくれた私は、ニヤニヤ笑っている清川君を睨みつけました。その時、タクシーが急にカーブを曲がったのです。私はバランスを崩して、清川君にもたれかかってしまいました。
「あっ」
清川君が私の腰に手を回してきました。私はどうしていいかわからず、ただ俯いているばかりです。
「・・・・」
車の揺れに合わせて、清川君の手がお尻へ下がってきます。
(清川君は私が上司の妻であることを忘れたのかしら? それともワインを飲みすぎておかしくなっちゃったのかしら?)
モゾモゾと動く掌をどうすることもできないまま、私は清川君の真意を測りかねていました。すると唐突に、清川君は吃驚することを耳元で囁いたのです。
「奥さんが好きです」
一瞬、私は耳を疑いました。慌てて清川君の顔を見ると、いつもと違って真面目な表情をしています。
「オ、オバサンをからかって・・」
「いえ、ずっと奥さんに憧れていました」
その瞬間、私は下腹部に甘い痺れを感じたのです。その痺れは、静かな水面に生じた波紋のように、ゆっくりと全身へ広がっていきます。
「だ、だめよ・・いけないわ」
我に返った私は、前の座席にいる運転手を気にして、お尻にまとわりつく清川君の手を払い除けました。
「どうしてですか?」
「ど、どうしてって・・だって私は田口の妻であり、愛美の母親なのよ」
運転手に気づかれないように、私は声にならない声で叱りました。
「わかっていますよ。でも私にとって奥さんは妻でも母でもありません。一人の女であるだけです」
私は心臓が止まりそうになりました。ただ清川君にお尻を触られるまま、口をパクパクさせているしかありませんでした。やがてタクシーが家の前で止まりました。
「奥さん、今夜は楽しかったです。おやすみなさい」
そう言うと、清川君は降りようとする私のあごを手で押さえ、いきなり口唇を重ねてきたのです。
「う、ううっ」
驚くほどの早業でしたが、私はしっかりと清川君の口唇を感じていました。 清川君を乗せたタクシーが遠ざかって行きます。
そのテールランプを眺めたまま、私は心の整理がつかず、しばらくマンションの近くでぼんやりとたたずんでいました。
私は、主人と娘、そして今の生活を愛しています。少女の頃から思い描いてきた幸せです。この幸せを守るため、私は良妻賢母であることを心がけてきました。 そんな平和な日常に、清川君は土足で踏み込んできたのです。 でも私は清川君を拒めませんでした。
心のどこかで、こうなることを期待していたのかもしれません。現実にはあり得ないトレンディドラマに憧れるように、私は非日常の恋愛を密かに夢見ていたのです。
もう一人の私。
それは主人と娘を裏切ってでも、清川君に淡い恋心を抱く女の私だったのです。 どちらが本当の私なのでしょうか? その答えも出せないまま、私はエントランスを抜け、エレベーターのボタンに手をかけました。
ただ一つ確かなことは、下着をはしたないほど濡らしていることだけでした。
つづく・・・








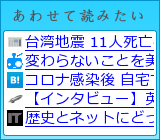


 を目指して…
を目指して…
 応援よろしくお願いします
応援よろしくお願いします



