「禁断の遺伝子」第三章・・・(紅殻格子)
※小説を読まれる方へ・・・
更新記事は新着順に表示されますので小説を最初から順追って
お読みになりたい方は、左のカテゴリー(各小説)を選択していただければ
第一章からお読みいただけるようになっております ※
『禁断の遺伝子』・・・・紅殻格子
三・
妻とはセックスレスだった。
妻は三十八歳、今がまさに女盛りのはずである。
ところがここ数年、夫婦の性交渉は途絶えていた。
それどころか新婚の頃から夫婦が肌を合わせた頻度は、
一年にわずか二三回程度しかなかった。
原因は妻が性を拒んでいるからだった。
周一がどれだけ尽くしても、妻は性の悦びを声に出さなかった。
不感症ならば諦めもつく。
だが間違いなく妻の体は、周一の愛撫に小さく痙攣して応えていた。
「いけない・・こんなのダメ・・」
ところが妻は、やっと疼き出した悦楽の芽を、強靭な理性で次々に摘み取った。
まるで性に溺れることが罪悪であるかのように、
妻は必死に歯を食いしばり、体に湧き上がる悦びを押し殺してしまうのだった。
新妻の恥じらいならばそれも初々しい。
だが尼僧を抱くような夫婦生活に、周一の淫欲も自然と萎えて行かざるを得ない。
男にとって女の喘ぎ声はご褒美なのだ。
それがなければ男の淫欲は衰え、妻を誘う気力すら失ってしまう。
はっと周一は我に返った。
「ねえ、もう欲しい・・お願い・・早く入れて・・」
すでに玲子の花芽は、淡いピンク色の突起を剥き出しにしていた。
そして充血した花襞からは淫蜜が滴り、シーツにはしたない染みをつくっていた。
周一は玲子の両脚をM字に開くと、整った翳りの下に肉茎を宛がった。
「はう・・突いて・・」
肉茎を押し出すや、花奥はヌルリとそれを呑み込んだ。
「ああっ、入って来る・・あうっ・・」
玲子はぐっと上半身を仰け反らせ、両手でシーツを鷲づかみにした。
「こんな老体に二回もさせるとは、本当にスケベな女だな」
「ううん、言わないで・・だって、ああっ・・体が勝手に感じちゃうの・・」
焦らすように周一はゆっくりと肉茎を出し入れする。
「ふん、オマンコに入れてもらえれば、別に俺じゃなくても感じるんだろう?」
「ううっ、そんなことないわ・・あなただけよ・・ああ、お願い、もっと動かして・・」
「彼氏に入れられても感じないのか?」
「あうぅ・・そうよ・・課長のチンポが一番いいの!」
周一は動きを少し大きくした。
玲子の淫肉が肉茎にねっとりと絡みつき、クチュクチュと卑猥な音を響かせる。
「本当かな・・よし、次に逢うときはカップル喫茶へ行って試してみよう」
「ああん・・カ、カップル喫茶?」
同伴喫茶から発展したカップル喫茶は、男と女の性をお互いに見せ合う場である。
覗き合える個室タイプの店と、オープンスペースで相互観賞できる店がある。
最近は過激なカップルが増え、見せ合うどころか、
スワッピングの相手を探す発展場になっている。
「そうだ。俺が見ている前で他の男に貸し出してやる。
その男に犯されて感じなければお前を信じよう」
「い、嫌・・そんなの変態じゃない・・」
「ふ~ん、行きたくないの?」
周一は熱い花奥から、ゆっくりと肉茎を抜く素振りをした。
「だめ、抜いちゃ嫌・・ああん、カップル喫茶に行くから・・もっと激しく突いて・・」
玲子は周一を仰向けに押し倒すと、股間の上に跨って自分から腰を振った。
「いいっ、気持ちいい・・ああ、私、犯されるのね・・
あなたの見ている前で、見ず知らずの男達に犯されるのね・・」
「お前は誰にでも体を開くメス奴隷になるんだ。
たくさんの男に犯されて、精液をオマンコに注ぎ込まれるんだぞ」
玲子の腰の動きに併せて、周一は下から強く突き上げた。
「あっ、あっ・・メス奴隷になりたい・・たくさんの男に犯されたい・・
ああっ、もうだめ・・いく・・いっちゃう!」
玲子は周一の上で天を仰ぐと、カクカクと体を小刻みに痙攣させ、
崩れ落ちるように胸板にしなだれかかってきた。
周一は熱い花奥めがけて、二度目となる精液を激しく撃ち上げた。
焦点が合わないトロンとした瞳で、玲子は乾き切った口唇を重ねてきた。
(可愛い女だ)
周一はそう心中で呟くと、汗ばんだ玲子の体を強く抱いた。
カップル喫茶で何人もの男に抱かれる玲子を想像して、
周一はまだ衰えない己の肉茎をゆっくりと引き抜いた。
続く・・・




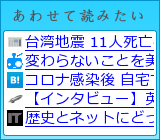


 を目指して…
を目指して…
 応援よろしくお願いします
応援よろしくお願いします



