二十三夜待ち 第十三章
FC2 Blog Ranking
昭和二十九年。
二十五歳になった小鶴は、天から射し込む光明を見た。
それは行商だった。
収穫した野菜を背負えるだけ背負って都会へ売りに行く。
行商は近郊農家にとって貴重な現金収入であり、女達の仕事だった。
人通りの多い街中で茣蓙を敷き、物乞いにも似た姿で農作物を商うことは、自尊心が高過ぎる男達にはできない仕事なのかもしれない。
朝の五時に起きて始発の房総東線に乗る。
背中に五十キロ、両手で二十キロほどの野菜を担いで都会へ向かう。
午前中に商いを済ませて家に戻り、翌日の農作物を収穫して荷造りを済ませ、夕飯の支度や家事を終えて就寝する厳しい生活だった。
小鶴も夫に命じられて行商へ行かされた。
初めて行商に出た小鶴は、村の女達とかち合わないよう川崎の工場労働者が住む地域へ向かった。
そこは路地裏にあばら家がひしめくスラムだった。
蕎麦屋の軒下を借りて野菜を並べてはみたが、行き交う人々に向かって売り声も出せず、しばらくはただ俯いて座っているばかりだった。
下町の女達は人情に厚い。
恥ずかしそうにもじもじする小鶴に、割烹着姿のおかみさん連中が気遣って声をかけてくれた。
「あんた商売は始めてかい?」
「おや、いい茄子じゃないか。ひと山貰おうかね」
「ちょっと、山田の奥さん、この娘初めての行商で難儀しているのさ。可哀想だから近所の人を呼んできて、荷物を捌いてあげようじゃないの」
その日はあっと言う間に野菜は売れてしまった。翌日からは一人二人と馴染客が増え、世間話に花を咲かすほど自然と街に溶け込んでいった。
小鶴は行商が楽しくなった。
商いする喜びや都会の華やかさは勿論、多くの人々と触れ合う喜びは、狭い田舎では決して得られない経験だった。
そして何より、夫や舅姑から解放される時間を持てることが一番の幸せだった。
続く…
 皆様から頂く
皆様から頂く が小説を書く原動力です
が小説を書く原動力です
「黄昏時、西の紅色空に浮かぶ三日月」に戻る




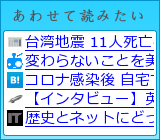


 を目指して…
を目指して…
 応援よろしくお願いします
応援よろしくお願いします



