『追憶の白昼夢』 第九章
『追憶の白昼夢』
FC2 Blog Ranking
(九)
その後はありふれたお互いの仕事の話や、共通の友人の噂話が続いた。
しかし私が本当に聞きたかった核心は、喉元まで出かかっていたものの、最後まで言葉にできなかった。
(彩香、お前は今、幸せなのか?)
それが私の心にわだかまっている疑問だった。
恋愛に関してよく世間で言われることがある。
男は過去の女を一生引き摺り続けるが、女は現在恋愛している男しか目に見えなくなると言う。
その法則が正しいとすれば、結婚した女が昔つきあっていた男に会いたいと連絡してくるのは、その女が不幸であるからに他ならない。
今日一日彩香と共にいても、自分から夫や家庭のことを話そうとしなかった。
いや、どちらかと言えば避けようとする素振りが見えた。
しかし先ほど強引に話を切り出した印象では、亭主は彼女の言いなりの従順な男で、暴力や博打、女遊びをして妻を顧みないタイプではないようだ。
(亭主を愛していないのか)
私は彩香の心中を推し測った。
家を継がなければならない彩香は、地元の公務員と、婿養子に入るという条件だけで結婚を決めてしまったのではないか。
熱烈な恋愛とは無縁に、無難な男を選んでしまったのではないか。
その愛してもいない男との生活の欝積から、電話で私に救いを求めてきたのであろうか。
私は彩香がもし不幸な結婚生活を送っているのなら、黙って見過ごすことはできないと思った。
妻子を捨てて、彩香とやり直すことはできない。
しかし非力ではあるが、彩香の心を癒すために出来うる限りのことをしてやりたい―。
私は密かにそう心に誓った。
山手のイタリア料理店を出た時、すでに時計は八時を回っていた。
土曜日の夜、山手の丘の上をくねる道に、人通りが絶えることはない。
特に外人墓地や港の見える丘公園辺りには、若いカップルが多くたむろしていた。
「飲酒運転は危ないわよ」
車がカーブの急な谷戸坂から元町へ向かうと、助手席の彩香が心配そうに言った。
「大丈夫だよ。そんなに飲んでないから」
「嘘。だってワイン一本空けちゃったじゃないの」
「ワイン一本ぐらい平気だよ。若い頃は一升瓶一本飲んでも、けろっとしてたさ」
「馬鹿、もう若くないの」
そう言うと、彩香は私の膝の上に手を置いた。
「ねえ、ホテルで休んでいったら?」
私は急ブレーキを踏みそうになった。
私の膝の上に置かれた彩香の掌が、そっと撫でるように太股へ動いた。
「いいでしょう?」
艶かしく甘い鼻声が、私の理性を激しく揺さぶった。
彩香と再会する前から、私はこうなることを夢想していた。
彩香もそれを望んでいる。
平凡な日常から逃避して、懐かしい十五年前の夢に浸っていたいのだ。
卒業とともに封じ込めた夢の小箱だけが、今の彼女の救いなのだ。
「彩香…」
私は足に置かれた彩香の掌を強く握った。
二人を乗せた車は、みなとみらいのホテルへ向けて夜の横浜を走り抜けた。
つづく…
 皆様から頂く
皆様から頂く が小説を書く原動力です
が小説を書く原動力です



「黄昏時、西の紅色空に浮かぶ三日月」に戻る
FC2 Blog Ranking
(九)
その後はありふれたお互いの仕事の話や、共通の友人の噂話が続いた。
しかし私が本当に聞きたかった核心は、喉元まで出かかっていたものの、最後まで言葉にできなかった。
(彩香、お前は今、幸せなのか?)
それが私の心にわだかまっている疑問だった。
恋愛に関してよく世間で言われることがある。
男は過去の女を一生引き摺り続けるが、女は現在恋愛している男しか目に見えなくなると言う。
その法則が正しいとすれば、結婚した女が昔つきあっていた男に会いたいと連絡してくるのは、その女が不幸であるからに他ならない。
今日一日彩香と共にいても、自分から夫や家庭のことを話そうとしなかった。
いや、どちらかと言えば避けようとする素振りが見えた。
しかし先ほど強引に話を切り出した印象では、亭主は彼女の言いなりの従順な男で、暴力や博打、女遊びをして妻を顧みないタイプではないようだ。
(亭主を愛していないのか)
私は彩香の心中を推し測った。
家を継がなければならない彩香は、地元の公務員と、婿養子に入るという条件だけで結婚を決めてしまったのではないか。
熱烈な恋愛とは無縁に、無難な男を選んでしまったのではないか。
その愛してもいない男との生活の欝積から、電話で私に救いを求めてきたのであろうか。
私は彩香がもし不幸な結婚生活を送っているのなら、黙って見過ごすことはできないと思った。
妻子を捨てて、彩香とやり直すことはできない。
しかし非力ではあるが、彩香の心を癒すために出来うる限りのことをしてやりたい―。
私は密かにそう心に誓った。
山手のイタリア料理店を出た時、すでに時計は八時を回っていた。
土曜日の夜、山手の丘の上をくねる道に、人通りが絶えることはない。
特に外人墓地や港の見える丘公園辺りには、若いカップルが多くたむろしていた。
「飲酒運転は危ないわよ」
車がカーブの急な谷戸坂から元町へ向かうと、助手席の彩香が心配そうに言った。
「大丈夫だよ。そんなに飲んでないから」
「嘘。だってワイン一本空けちゃったじゃないの」
「ワイン一本ぐらい平気だよ。若い頃は一升瓶一本飲んでも、けろっとしてたさ」
「馬鹿、もう若くないの」
そう言うと、彩香は私の膝の上に手を置いた。
「ねえ、ホテルで休んでいったら?」
私は急ブレーキを踏みそうになった。
私の膝の上に置かれた彩香の掌が、そっと撫でるように太股へ動いた。
「いいでしょう?」
艶かしく甘い鼻声が、私の理性を激しく揺さぶった。
彩香と再会する前から、私はこうなることを夢想していた。
彩香もそれを望んでいる。
平凡な日常から逃避して、懐かしい十五年前の夢に浸っていたいのだ。
卒業とともに封じ込めた夢の小箱だけが、今の彼女の救いなのだ。
「彩香…」
私は足に置かれた彩香の掌を強く握った。
二人を乗せた車は、みなとみらいのホテルへ向けて夜の横浜を走り抜けた。
つづく…
 皆様から頂く
皆様から頂く が小説を書く原動力です
が小説を書く原動力です
「黄昏時、西の紅色空に浮かぶ三日月」に戻る




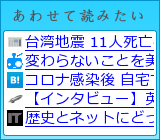


 を目指して…
を目指して…
 応援よろしくお願いします
応援よろしくお願いします



