『追憶の白昼夢』 第五章
『追憶の白昼夢』
FC2 Blog Ranking
(五)
港北から第三京浜に乗り、横浜新道を使って横浜横須賀道路に入る。
渋滞もなく、三十分も走ると横須賀に着いた。
車はインターを出て、葉山へ向けてしばらく山路を走った。
そして長いトンネルを抜けると、突然目の前に相模湾が開けた。
「まあ、綺麗!」
彩香は眩しさに目を細めた。
フロントガラスの全面に広がる無数の光の粒子をちりばめた群青色の海が、遥か彼方に緩やかな水平線を描いている。
その無辺のキャンバスには、散在する小磯と松林、遠くに白い帆を張る数艇のヨットが、上品な筆遣いで添えられている。
彩香と私を乗せた車は、古より避寒地として別荘の多い佐島を通り、城ケ島へと国道を南下した。
城ケ島はマグロの水揚げ港として有名な三崎の対岸の島で、三浦半島の最南端に位置している。
北原白秋の『城ケ島の雨』の詩碑も残る景勝地である。
私達は車を降りて磯伝い散策を始めた。
「ああ、懐かしい。この海の匂い、あの頃と変わらないわ…」
彩香は波打ち際に立つと、磯の香りを大きく吸い込んだ。
海を渡る潮風が、背中まで届く緩やかにウェーブした髪をそよがせる。
「ねえ、覚えてる?デートでここに初めて来た時のことを。あの頃は二人とも学生で車なんかなくて、電車とバスを乗り継いで来たじゃない」
「ああ、確か横浜から二時間ぐらいかかったよな」
「うん、帰りの電車の中で哲ちゃんが囁いてくれた一言が今でも忘れられないわ。お前を一生離さないって…その夜、初めて二人は結ばれたのよ」
彩香は私の腕をきつく抱いた。
柔らかい乳房の感触が、熱く衣服越しに伝わってくる。
「あ、あの頃は、お互いに、若かったしな」
私は困惑の余り、上の空で相槌を打った。
彩香が私の腕を強く抱えるのは、昔つきあっていた頃からの癖だった。
大学時代―。
私たちは同じサークルの仲間だった。
そのサークルはテニスやスキーのような軟派なものではなく、養護施設の子供たちと交流を持つボランティア・サークルだった。
従ってそこに集う仲間は、当時の大学生にありがちな無気力で軽い人間ではなく、真面目な社会と向き合おうとする者が多かった。
中でも彩香はひときわ熱心に活動していた。
親のいない子供たちにいつも母親の如く優しく接していた。
しかもなぜ地味なボランティア・サークルに入ってきたのか皆が訝しがるほど、彩香は美しかった。
アンティークの西洋人形にも似た円らな瞳が、周囲の男たちの恋心を誘った。
当時彼女に言い寄る輩も数多くいたらしい。
しかしサークルに熱中していたからか、はたまた女として幼すぎたのか、彼女は男たちの求愛を全く受けつけなかった。
そして『男嫌い』とか『鋼の処女』とか、陰で渾名されるようになった。
無論、当時他ならぬ私も彼女に密かに憧れていた。
しかし二枚目でもない私は、とても彼女に想いを打ち明ける勇気など持ち合わせていなかった。
ところが会津から上京して一人暮らしする彩香のアパートが、偶然にも私の家の近くにあり、サークル活動のある日にはよく二人で帰る機会に恵まれた。
つづく…
 皆様から頂く
皆様から頂く が小説を書く原動力です
が小説を書く原動力です



「黄昏時、西の紅色空に浮かぶ三日月」に戻る
FC2 Blog Ranking
(五)
港北から第三京浜に乗り、横浜新道を使って横浜横須賀道路に入る。
渋滞もなく、三十分も走ると横須賀に着いた。
車はインターを出て、葉山へ向けてしばらく山路を走った。
そして長いトンネルを抜けると、突然目の前に相模湾が開けた。
「まあ、綺麗!」
彩香は眩しさに目を細めた。
フロントガラスの全面に広がる無数の光の粒子をちりばめた群青色の海が、遥か彼方に緩やかな水平線を描いている。
その無辺のキャンバスには、散在する小磯と松林、遠くに白い帆を張る数艇のヨットが、上品な筆遣いで添えられている。
彩香と私を乗せた車は、古より避寒地として別荘の多い佐島を通り、城ケ島へと国道を南下した。
城ケ島はマグロの水揚げ港として有名な三崎の対岸の島で、三浦半島の最南端に位置している。
北原白秋の『城ケ島の雨』の詩碑も残る景勝地である。
私達は車を降りて磯伝い散策を始めた。
「ああ、懐かしい。この海の匂い、あの頃と変わらないわ…」
彩香は波打ち際に立つと、磯の香りを大きく吸い込んだ。
海を渡る潮風が、背中まで届く緩やかにウェーブした髪をそよがせる。
「ねえ、覚えてる?デートでここに初めて来た時のことを。あの頃は二人とも学生で車なんかなくて、電車とバスを乗り継いで来たじゃない」
「ああ、確か横浜から二時間ぐらいかかったよな」
「うん、帰りの電車の中で哲ちゃんが囁いてくれた一言が今でも忘れられないわ。お前を一生離さないって…その夜、初めて二人は結ばれたのよ」
彩香は私の腕をきつく抱いた。
柔らかい乳房の感触が、熱く衣服越しに伝わってくる。
「あ、あの頃は、お互いに、若かったしな」
私は困惑の余り、上の空で相槌を打った。
彩香が私の腕を強く抱えるのは、昔つきあっていた頃からの癖だった。
大学時代―。
私たちは同じサークルの仲間だった。
そのサークルはテニスやスキーのような軟派なものではなく、養護施設の子供たちと交流を持つボランティア・サークルだった。
従ってそこに集う仲間は、当時の大学生にありがちな無気力で軽い人間ではなく、真面目な社会と向き合おうとする者が多かった。
中でも彩香はひときわ熱心に活動していた。
親のいない子供たちにいつも母親の如く優しく接していた。
しかもなぜ地味なボランティア・サークルに入ってきたのか皆が訝しがるほど、彩香は美しかった。
アンティークの西洋人形にも似た円らな瞳が、周囲の男たちの恋心を誘った。
当時彼女に言い寄る輩も数多くいたらしい。
しかしサークルに熱中していたからか、はたまた女として幼すぎたのか、彼女は男たちの求愛を全く受けつけなかった。
そして『男嫌い』とか『鋼の処女』とか、陰で渾名されるようになった。
無論、当時他ならぬ私も彼女に密かに憧れていた。
しかし二枚目でもない私は、とても彼女に想いを打ち明ける勇気など持ち合わせていなかった。
ところが会津から上京して一人暮らしする彩香のアパートが、偶然にも私の家の近くにあり、サークル活動のある日にはよく二人で帰る機会に恵まれた。
つづく…
 皆様から頂く
皆様から頂く が小説を書く原動力です
が小説を書く原動力です
「黄昏時、西の紅色空に浮かぶ三日月」に戻る




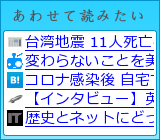


 を目指して…
を目指して…
 応援よろしくお願いします
応援よろしくお願いします



