『追憶の白昼夢』 第六章
『追憶の白昼夢』
FC2 Blog Ranking
(六)
二年生になったばかりの春の夜、サークルのコンパで帰りが遅くなり、いつものように私は彩香をアパートまで送っていくことになった。
彩香も私もかなり酔っていた。
「いつも遠回りさせてごめんね。速水君だって迷惑でしょう?」
「そんなことないよ。男は美人と一緒に歩いているだけで楽しいものさ」
酔っているからか、普段は言えないこんな軽口も飛び出す。
薄暗い街燈の続く人通りのない夜道を歩きながら、二人は他愛もない会話を紡いでいった。
青白い街燈を過ぎるたびに、二人の寄り添う影が伸びては闇に消えていく。
「速水君…」
彩香はやがてぽつんと呟くと歩みを止めた。
そして何か思い詰めたように俯いてしまった。
「どうしたの?具合でも悪いの?」
彩香は黙ったまま小さく首を振った。
「速水君…去年の夏の合宿で、私がある先輩からしつこくからまれたのを覚えてる?」
「ああ、あれ。もう半年も前の話だよ」
「あの時、速水君が止めに入ってくれたでしょう」
「うん、酔うと人が変わるんだよね。昼間はいい先輩なんだけどな」
「あ、あのね、その時ね、その、すごく嬉しかったの…で、でも速水君って、誰にでも優しいから…その、こうして送って貰うのだって、他の女の子にも、そうかなって思ったり、でも、ずっと、す、好きで―」
地面を向いたまま口ごもる彩香の肩をそっと抱きしめた。
彩香は小刻みに震えている。
私が信じられないまま、今度は自分の想いを打ち明けると、彩香は黙って頷いた。
「男嫌いだとばかり思っていたよ」
「私は誰にでもついて行くような女じゃないだけよ」
緊張が解けたのか、彩香がようやく笑顔を見せた。
二人が初めて結ばれたのは、彩香が言った通り、城ケ島でデートしたその夜のことだった。
告白から一週間後の週末だった。
ファミリーレストランで夕食を済ませた私達は、彼女のアパートでのんびりと強行軍の疲れを癒すことにした。
「ねえ、哲ちゃん」
彩香は、つきあうようになってから呼び始めた名で、私を呼んだ。
「帰りの電車の中で言ったこと、覚えてる?」
彩香は壁に凭れてテレビを見ていた私の隣に座って聞いた。
「何?」
「もう忘れたの?酷いわ、やっぱり口からでまかせだったのね」
彩香は私の足をつねると、頬を膨らませて拗ねてみせた。
「痛っ、覚えてるよ。一生、その何だよ、離したくないって…」
と私が口籠ると、彩香は急に抱きついて口唇を重ねてきた。
息遣いが荒い。もじもじと体を摺り寄せてくる。告白の夜から、キスは何度となく交わしていた。
だが私は、まだ処女だという彼女と一線を越えるタイミングと勇気がなかった。
おとなしい彼女の思いがけない行動に驚いたが、いとおしさがこみあげてきて、私は彼女を抱き締めると、優しくベッドに押し倒した。
「哲ちゃんのお嫁さんにしてくれる?」
彩香はうわ言のように何度も何度も繰り返した。
私は無言で頷きながら、彼女のTシャツをゆっくりと捲り上げた。
「恥ずかしい…」
つづく…
 皆様から頂く
皆様から頂く が小説を書く原動力です
が小説を書く原動力です



「黄昏時、西の紅色空に浮かぶ三日月」に戻る
FC2 Blog Ranking
(六)
二年生になったばかりの春の夜、サークルのコンパで帰りが遅くなり、いつものように私は彩香をアパートまで送っていくことになった。
彩香も私もかなり酔っていた。
「いつも遠回りさせてごめんね。速水君だって迷惑でしょう?」
「そんなことないよ。男は美人と一緒に歩いているだけで楽しいものさ」
酔っているからか、普段は言えないこんな軽口も飛び出す。
薄暗い街燈の続く人通りのない夜道を歩きながら、二人は他愛もない会話を紡いでいった。
青白い街燈を過ぎるたびに、二人の寄り添う影が伸びては闇に消えていく。
「速水君…」
彩香はやがてぽつんと呟くと歩みを止めた。
そして何か思い詰めたように俯いてしまった。
「どうしたの?具合でも悪いの?」
彩香は黙ったまま小さく首を振った。
「速水君…去年の夏の合宿で、私がある先輩からしつこくからまれたのを覚えてる?」
「ああ、あれ。もう半年も前の話だよ」
「あの時、速水君が止めに入ってくれたでしょう」
「うん、酔うと人が変わるんだよね。昼間はいい先輩なんだけどな」
「あ、あのね、その時ね、その、すごく嬉しかったの…で、でも速水君って、誰にでも優しいから…その、こうして送って貰うのだって、他の女の子にも、そうかなって思ったり、でも、ずっと、す、好きで―」
地面を向いたまま口ごもる彩香の肩をそっと抱きしめた。
彩香は小刻みに震えている。
私が信じられないまま、今度は自分の想いを打ち明けると、彩香は黙って頷いた。
「男嫌いだとばかり思っていたよ」
「私は誰にでもついて行くような女じゃないだけよ」
緊張が解けたのか、彩香がようやく笑顔を見せた。
二人が初めて結ばれたのは、彩香が言った通り、城ケ島でデートしたその夜のことだった。
告白から一週間後の週末だった。
ファミリーレストランで夕食を済ませた私達は、彼女のアパートでのんびりと強行軍の疲れを癒すことにした。
「ねえ、哲ちゃん」
彩香は、つきあうようになってから呼び始めた名で、私を呼んだ。
「帰りの電車の中で言ったこと、覚えてる?」
彩香は壁に凭れてテレビを見ていた私の隣に座って聞いた。
「何?」
「もう忘れたの?酷いわ、やっぱり口からでまかせだったのね」
彩香は私の足をつねると、頬を膨らませて拗ねてみせた。
「痛っ、覚えてるよ。一生、その何だよ、離したくないって…」
と私が口籠ると、彩香は急に抱きついて口唇を重ねてきた。
息遣いが荒い。もじもじと体を摺り寄せてくる。告白の夜から、キスは何度となく交わしていた。
だが私は、まだ処女だという彼女と一線を越えるタイミングと勇気がなかった。
おとなしい彼女の思いがけない行動に驚いたが、いとおしさがこみあげてきて、私は彼女を抱き締めると、優しくベッドに押し倒した。
「哲ちゃんのお嫁さんにしてくれる?」
彩香はうわ言のように何度も何度も繰り返した。
私は無言で頷きながら、彼女のTシャツをゆっくりと捲り上げた。
「恥ずかしい…」
つづく…
 皆様から頂く
皆様から頂く が小説を書く原動力です
が小説を書く原動力です
「黄昏時、西の紅色空に浮かぶ三日月」に戻る




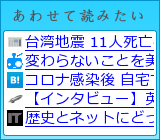


 を目指して…
を目指して…
 応援よろしくお願いします
応援よろしくお願いします



