『蟻地獄』 第六章
『蟻地獄』
六
千葉県津田沼市。
駅から徒歩で十五分離れた住宅地に、和彦が昨年購入した一戸建ての新居があった。
猫の額ばかりの庭には、もうつぼみをつけた朝顔が、勢いよく伸びる蔓をフェンスに絡ませている。
梅雨明けも近い土曜日の昼、高山家は賑やかな笑い声で溢れていた。
川崎が遊びに来ていた。
和彦が新しく買ったラジコン・ヘリが見たいと言う。
ところが自慢のヘリなどどこ吹く風、ビール缶片手に妻の手料理を貪っている。
「奥さんの手料理は最高です!」
「いやねえ、母に教わっただけだから田舎料理ばかりよ」
「それがいいんです。侘しい一人暮らしには、おふくろの味が一番うれしいんですよ」
「でも川崎君は北海道出身でしょう。私の沖縄料理が口に合うかしら?」
「ヘルシーな沖縄料理はブームですよ。でもこのゴーヤチャンプルー、店で食べるのよりよっぽど美味しいです」
川崎は料理を頬張りながら、ダイニングテーブルでキッチンの妻と話している。
そんな光景を横目に、和彦は独りリビングのソファで、忘れられたラジコン・ヘリを手慰みに磨くしかなかった。
会話は和彦を無視して続く。
「僕は沖縄出身のミュージシャンが大好きなんですよ」
「あら、私もよ。故郷の匂いがして帰りたくなっちゃう」
そのミュージシャンの話題で、二人の会話はますます盛り上がっていく。
疎外感が和彦を襲う。
(若い者同士で話が合うんだろうな)
和彦はまったくついていけないが、三十路を越えたばかりの佳美には、川崎と世代観が重なる部分があるのだろう。
佳美の笑顔が眩しい。
瓜実形をした小さな顔の輪郭が、肩まで伸びたダークブラウンの髪で飾られている。
きりっと吊り上がった柳眉、長い睫毛にくっきりと縁取られた悪戯っぽい瞳、そして端正な鼻梁と艶を含んだ口許には、まだ二十代半ばで通用する瑞々しさを保っていた。
つづく…
「黄昏時、西の紅色空に浮かぶ三日月」に戻る
六
千葉県津田沼市。
駅から徒歩で十五分離れた住宅地に、和彦が昨年購入した一戸建ての新居があった。
猫の額ばかりの庭には、もうつぼみをつけた朝顔が、勢いよく伸びる蔓をフェンスに絡ませている。
梅雨明けも近い土曜日の昼、高山家は賑やかな笑い声で溢れていた。
川崎が遊びに来ていた。
和彦が新しく買ったラジコン・ヘリが見たいと言う。
ところが自慢のヘリなどどこ吹く風、ビール缶片手に妻の手料理を貪っている。
「奥さんの手料理は最高です!」
「いやねえ、母に教わっただけだから田舎料理ばかりよ」
「それがいいんです。侘しい一人暮らしには、おふくろの味が一番うれしいんですよ」
「でも川崎君は北海道出身でしょう。私の沖縄料理が口に合うかしら?」
「ヘルシーな沖縄料理はブームですよ。でもこのゴーヤチャンプルー、店で食べるのよりよっぽど美味しいです」
川崎は料理を頬張りながら、ダイニングテーブルでキッチンの妻と話している。
そんな光景を横目に、和彦は独りリビングのソファで、忘れられたラジコン・ヘリを手慰みに磨くしかなかった。
会話は和彦を無視して続く。
「僕は沖縄出身のミュージシャンが大好きなんですよ」
「あら、私もよ。故郷の匂いがして帰りたくなっちゃう」
そのミュージシャンの話題で、二人の会話はますます盛り上がっていく。
疎外感が和彦を襲う。
(若い者同士で話が合うんだろうな)
和彦はまったくついていけないが、三十路を越えたばかりの佳美には、川崎と世代観が重なる部分があるのだろう。
佳美の笑顔が眩しい。
瓜実形をした小さな顔の輪郭が、肩まで伸びたダークブラウンの髪で飾られている。
きりっと吊り上がった柳眉、長い睫毛にくっきりと縁取られた悪戯っぽい瞳、そして端正な鼻梁と艶を含んだ口許には、まだ二十代半ばで通用する瑞々しさを保っていた。
つづく…
「黄昏時、西の紅色空に浮かぶ三日月」に戻る




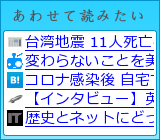


 を目指して…
を目指して…
 応援よろしくお願いします
応援よろしくお願いします



