「禁断の遺伝子」第十章・・・(紅殻格子)
※小説を読まれる方へ・・・
更新記事は新着順に表示されますので小説を最初から順追って
お読みになりたい方は、左のカテゴリー(各小説)を選択していただければ
第一章からお読みいただけるようになっております ※
『禁断の遺伝子』・・・・紅殻格子
十・
鴻巣はつかつかと蔵に入ってくると、周一が持っていた写真を取り上げた。
「あなた方にこの写真は必要ない」
「こ、鴻巣さん、あなたは一体古谷野家とどういう関係があるんですか?」
「世の中には知らない方がいいこともある。
幸いお嬢様も私に気づいていないようだし・・」
先ほどまでの低姿勢だった鴻巣とは打って変わり、
ぞんざいな態度で蔵を出て行こうとした。
「ちょっと待って下さい。あなたなら知っているんじゃないですか。
妻の月絵は亡くなった今も実父を憎んでいる。
実母もです。頑ななまでに月絵が両親を拒む理由を知りたいんです」
鴻巣は立ち止まった。
「・・お嬢様はまだ孝蔵様と静子奥様を許していないのか?」
「ええ。孫の顔もほとんど見せないほど」
「そこまで恨んでいたのか・・」
鴻巣は近くにあったダンボール箱に腰を下ろすと、
ぽつりぽつりと記憶を辿るように昔話を始めた。
二十三年も前の話だった。
「私はK町で小学校の教員をしていた・・」
当時檜原集落には近隣K町の分校があった。
三十代後半だった鴻巣は、三年間檜原分校へ異動の辞令を受けた。
檜原集落では、遠路分校に通う先生に感謝して、
月に二三度、有力者の孝蔵が教員を夕食に招くのが常になっていた。
ある春の夜、鴻巣はいつものように古谷野家で晩餐をふるまわれていた。
ちょうど夏休み前で、鴻巣も心の緩みからいつもより深酒した。
「鴻巣君、今夜は泊まって行きたまえ」
「しかしご迷惑でしょうから・・」
「でもそんなに酔っていたら、車は運転できませんよ」
着物姿の静子が食膳を片づけながら、細面の整った顔立ちで微笑した。
その静子の言葉に後押しされて、泥酔した鴻巣はK町の妻に外泊の電話をした。
深夜、鴻巣はなかなか寝つかれなかった。
安普請の自宅とは違い、どっしりした旧家の重みが神経を昂ぶらせていた。
「・・だめ・・聞こえちゃう・・」
鋭敏になった耳を澄ますと、襖の向こうから静子の声が微かに聞こえてきた。
「あん・・いや、あなた、感じる・・」
襖一枚隔てた先は孝蔵夫婦の寝室だった。
艶かしい静子の声が徐々に羞恥を失っていく。
その淫らな喘ぎ声は、聖職者とは言いながらも、
生身の男である鴻巣の下半身を直撃した。
鴻巣は気づかれないように襖をそっと開いた。
(えっ!)
煌々と明かりが灯る広い和室の布団の上で、
静子は胡坐座りの孝蔵に背後から抱きかかえられていた。
「ああっ、もう・・もうだめ・・」
乳房を揉まれ、両脚をM字に開かされている。
その丸見えになった花芯が、まるで鴻巣の好色心を見透かすかのように、
細く開いた襖の方へ向けられているのだった。
露になった花芽をグリグリと指で捏ねくりながら、
孝蔵が襖の合わせから覗いている鴻巣に声をかけた。
「鴻巣君、見ているだけじゃ体に悪いぞ。
こっちへ来て静子を一緒に犯してくれないか」
鴻巣はまるで夢遊病者のように、言われるままに襖を開けて隣室に導かれた。
続く・・・




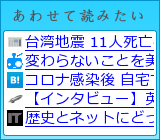


 を目指して…
を目指して…
 応援よろしくお願いします
応援よろしくお願いします



